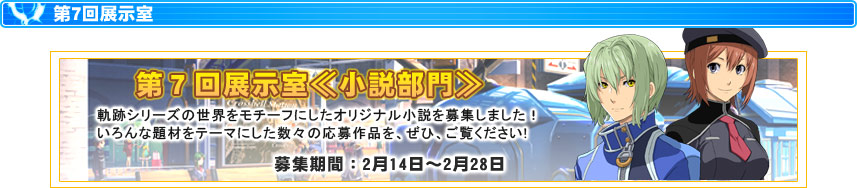■minami
| 【タイトル】 |
星が生まれるそのキセキ |
| 【作者】 |
minami |
その日、渡り鳥は、かつて見たこともないほどの、
アーツが放つの光を目にした。
爆発することで初めて認識される超新星。
そのたとえが大げさではないと、彼は感じた。
小さな家と、畑と、家畜小屋。私とお婆さん。
雪で包まれ、全ての音が閉ざされ、空はいつも灰色。
一度もここから外へ出たことはない。だけど優しい
お婆さんと二人、笑顔と共に暮らしていた。
ある日、旅人が訪れた。初めて会う外の人間。
笑顔が輝く少女と、その光を受けて、深い闇から
優しさを届けてくれているような少年だった。
沢山の話を聞いた。外の世界では、太陽と月が、
空で輝いているらしい。話の途中、鏡を覗いたら、
初めて見る顔をした私がいた。目が星のようだと
二人は笑った。
旅立つ二人を見送ると、お婆さんが憂いを含んだ
咎めるような目で、私を見つめていた。
—そういえば、私が夢中になっている時、お婆さんは
どこにいたんだろう。
「あなたには無理よ。外で何ができるというの。」
「そうだね。でも知ってしまったの、外の世界を、
私の中にある必然的な何かを。行かなくては
だめなのよ。」
そうは言っても、私にはアーツを操る力も、
クラフトもない。無力さに視線を泳がせた。
ふと小さな杖が目に留まった。綺麗な石が
はめ込まれた古い杖だ。不意にあの二人の姿が
浮かび、その手にしていた物とを重ねて杖を
見つめた。
「ねえ、これって。」
「そうよ。でも無理よ。ここは安定していて、
素晴らしいじゃないの。」
お婆さんの言葉の違和感に、私は確信を強めた。
「私には、これを使える力が・・・。」
「いけません!」
お婆さんは瞳をそらした。だけど強い語気とは
裏腹に、諦めの色が浮かんでいた。
どれぐらい時間が経っただろう。いつしか見つめ
合っていた。言葉は無く、それでも不思議と会話が
行き来していた。気づくと光が二人を朧にするかの
ように包んでいた。
「そう、だったんだ…。」
頭の中で二つの意識が廻っていた。お婆さんが
来た日の映像が浮かぶ。両親の死に涙する私が
握り締めた杖と、先端で輝く幻のクオーツ。
そして私の寂しさと、安らぎを求める心とが
生み出した…。
私の血に流れる力は、遠い祖先が隠したもので、
この場所が閉ざされた理由だったんだ。
でも私がそれを開放していいのだろうか。
そんな葛藤は嘘だ。決めたんだ。ああ、でも…。
目に溜まった涙で景色がゆがんだ。お婆さんは
どんな表情をしているのだろう。幻だけど、
現実だった。胸の鼓動も強く頷いているかのように
高鳴る。
—ありがとう、さようなら。
杖を振り下げた時、涙が散った。
視界が鮮明になった。だからまた泣いた。
止まらないほどに。そこにはもう、今まで私が
見てきたもの、人さえも、すべてが消えていたからだ。
感じたことのない何かが肌に触れた。これが風
なんだ。
木々が音を奏で出した。ささやかな旅立ちの音楽。
空には無数の輝く星。その一つとして、私は、今…。 |