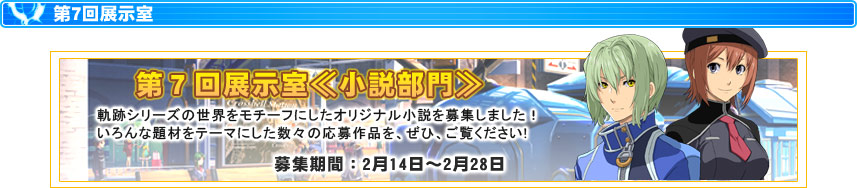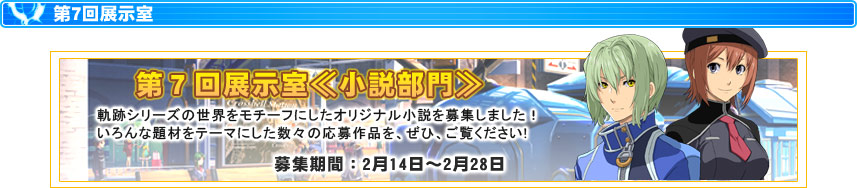■paparia
| 【タイトル】 |
吾輩は猫である〜コッペの瞳から〜 |
| 【作者】 |
paparia |
私はコッペ。この大都会の目まぐるしく移りゆく時間
と人々を、街外れにあるこの古ぼけたビルで見守って来
た、黒猫だ。
この建物から声が消えてしばらく、平穏な暮らしを堪
能していたのだが、ある日若い人間たちが数名住み着い
た。また騒がしくなるのだろうか。
その日の夜、青年が一人私のところへやって来た。先
住民に敬意を払うことのできる、今時感心な青年であっ
た。何か悩んでいたようにも見えたのだが、いかんせん
私は人間の言葉を発することができない。若いうちは、
そうやって悩み抜き、自ら答えを出すことも必要なの
だ。
すっかり春めき、私の毛が生え換わり始めた頃、ビル
に白い狼がやってきた。別段恐れるわけではないが、私
に食事を与えに来る若者たちが苦笑いをしているのを見
ると、彼らのほうが戸惑っているようだった。
ツァイトと名乗ったその狼は、彼らの仕事に付き合っ
たり手助けしたりと気まぐれな毎日を送っている。物好
きな奴だ。
私も彼らのことは気に入っている。うるさくしないし
昼寝の邪魔もしない。よこしてくる食事は美味だ。義に
は義を持って返す私は、ささやかな礼をもって返してい
るつもりだ。
あの夜、悩みに表情を曇らせていた青年は、今では晴
れ晴れとした笑顔を見せていた。はて、どこかで見た眼
差しのような気がするが、思い出せない。私も歳だ。
この頃、街の様子がおかしい。ヒゲがピリピリするほ
どに、街中が何か不穏な空気に包まれている。人々の表
情も、どこか不安げだ。
だがこのビルの中では、毎日が晴天のようだった。新
しくやってきた子供が太陽のような笑顔を振りまき、若
者たちを癒している。無思慮に触れてくる子供はあまり
好きではない私だが、この子供はまるで私の考えが解っ
ているようで、不作法に触れたりはしない。それは心地
よかったし、その子供自体も嫌いではない。この頃は外
に出るより、建物に居ることが多くなった。
だが僅かに張り詰めた青年達の表情に、私はこれから
何かが起こるであろうことを予感した。
そしてそれは的中した。
建物を無骨な連中が取り囲み、とんでもない勢いで破
壊活動を開始したのだ。青年達が撤退するとそれは止
み、謎の連中は彼らを追って行く。私はそれを屋上から
眺めていた。薄情などと言うなかれ。私には私の、彼ら
には彼らのすべきことがある。そして今まさに彼らは、
それを成しに行ったのだ。
私にできることは、あの強い意志を湛えた瞳の青年達
が帰るこの場所で、いつものように待っていることだ。
また平穏な日常が戻って暫く、ようやく思い出したの
だが。
あの青年に似た眼差しの男に、昔会ったことがある。
私がまだ幼い子猫だった頃、私に構ってくる男がいた
のだ。大きな手で無粋な撫で方をされたものだが、不思
議と嫌ではなかったのを覚えている。
あの男は、今はどうしているだろう。
いつかまた会いたいと、まだ若い彼らを見ていて思っ
た。 |