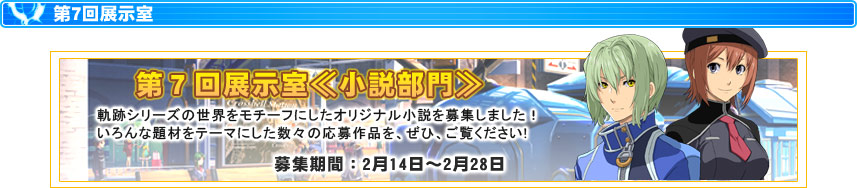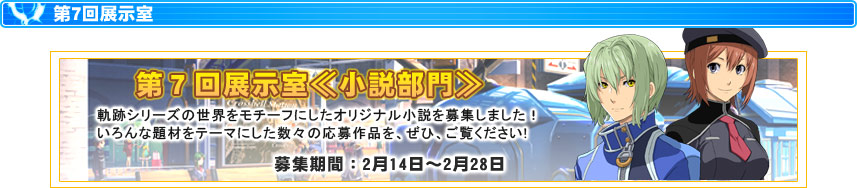■石園 悠
| 【タイトル】 |
サレクと魔法と猫(10/10) |
| 【作者】 |
石園 悠 |
いやはや、と男は呆れたように呟いた。
「お前さんか? あの黒猫に何か魔術をかけたのは」
「とんでもない」
ローブ姿の男は大きく首を振った。
「あれはサレク自身の力ですよ、アースト」
「猫を人間にしちまうような強い魔力が、あのガキん
ちょに?」
「少し違います」
笑みを浮かべてラヴネルは否定した。
「彼はいつでもジアンナと一緒にいました。身よりの
ない彼にとって、唯一の家族のように。そのことが彼と
彼女の間に大きな絆を作ったんです」
「だからって、猫は人間に化けんだろう」
「おや、知らないんですか? 猫というのはもともと
魔性の生き物です。しかも黒猫というのは魔術によく
馴染む。昔から、魔女が黒猫を連れるという伝承がある
でしょう?」
「いや、だからって……」
「化け猫伝承の八割以上は、事実が基になっています。
だいたい、狐が人間に化けていたことについては抵抗
ないようなのに、どうして猫だと不思議がるんです?」
「いや、狐は化けるって言うだろう」
「猫だって言いますでしょう?」
「いや……」
アーストはどう返していいか判らなくなったよう
だった。
「通常、人にまで変化(へんげ)するのは長く生きた猫
ですが、サレクの無意識の愛情とそれを受け止めた
ジアンナの間に、通常以上のことが起こったという
ところですね」
「『通常』ねえ」
戦士はどうにも納得しがたい様子だった。それを見て
魔術師は笑う。
「さあ、もう行きましょうか」
「ガキんちょに会っていかないのか?」
「ようやく時間ができましたから授業の続きをとも
思いましたけれど、私の手はもう必要ないかと」
「どうしてだ」
「そりゃあ」
ラヴネルは澄まし顔で肩をすくめた。
「魔法のことはジアンナもよく知っていますからね」
どさり、と少年は酒場の椅子に座り込んだ。
いったい何が起きたのか。だいたいのところは判って
いた。ただ納得がいかないと言おうか、本当に起きた
ことなのか自信がないと言おうか。
にゃあ、と黒猫は隣の椅子の上で毛づくろいをして
いた。
そう。猫だ。誰がどこからどう見ても。
だが、人間だった。さっきまで。少なくともそう
見えた。
「……ジアンナ」
サレクは話しかけた。黒猫に話しかける癖は昔から
あるもので、彼にとっては何ら奇妙なことでは
なかった。
「お前……いや、でも」
(何よ?)
「うひゃっ!?」
頭のなかに声がして、サレクは素っ頓狂な悲鳴を
上げた。周りが不審な目で見るのに愛想笑いを浮かべて
どうにかごまかす。
「お、お前か?」
(そうよ)
当然のように声——ジアンナは返す。
(これまでは自重してたんだけど。そろそろいいかなっ
て)
「話せたのか!?」
(最初からって訳じゃないわ。あんたが力を使うに
つれて、あたしもできることが増えたの)
「……何で」
(あんた何にも知らないのね)
ジアンナは呆れ声だった。
(仕方ない。あの女狐がまた狙ってきても面倒だし)
黒髪の少女がにやっと笑った気がした。
(これからあたしが、教えてあげる) |