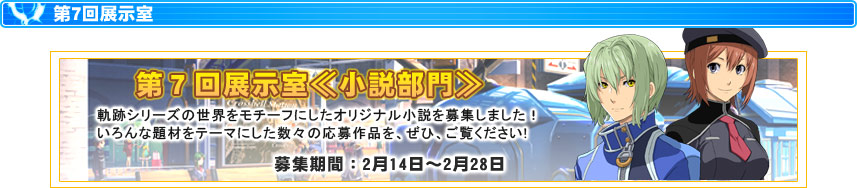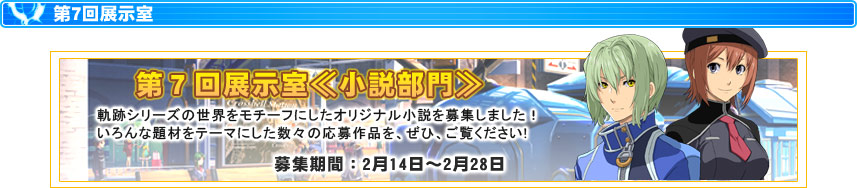■おぐら
| 【タイトル】 |
Etude of the Ruin |
| 【作者】 |
おぐら |
聖堂にオルガンの音色が響く。
奏でているのは祭服を纏い、眼鏡をかけた青年。彼の
指はひたすらに鍵盤上を踊る。
「やあ、熱心だね」
声に男の指が止まった。振り向いた先には世話になっ
ている司教の姿がある。
「ええ、向上心だけは忘れたくないと思っているもので
すから」
青年の柔和な笑みに司教は一つの問いを投げかけた。
「配属希望は決まったかね?」
「……いえ」
青年の金耀石に似た瞳が翳りを帯びる。入信して5年。
彼は選択を迫られていた。
「君の頭脳、向上心……どれも誰にも引けを取らない。
どこでも上手くやっていけるはずだ」
司教の言葉にも青年は俯くのみ。
「もう暫く時間を頂けませんか? どうしても心を決め
かねるので」
青年はそう頼み込み、一つの決意を固めた。
それから数時間後。
青年は荒れ果てた大地へと降り立っていた。
幼き日を過ごしたノーザンブリア。突如顕れた「塩の
杭」により壊滅した場所。
当時のような大量の塩こそ無かったものの、未だ草木
すら育たぬ不毛の地。今は教会の管理下に置かれ一般人
は入る事すら許されていない。青年も上層部にかけあい
許しを得てやってきたのだ。
ふと、廃都を歩む彼の瞳に、あり得ない光景が写し出
された。
逃げ惑う人々、降りしきる塩の塊。人が、物品が、建
物が、白に取り込まれ崩れ落ちる。
それは、幼き日に目にした崩壊の再現に他ならなかっ
た。
襲い来る塩に思わず青年は腕で顔を覆う。暫しして何
事も無い事に気づき腕を避けると、光景は嘘のよう立ち
消え、ただ廃墟が残るのみ。
「……いや、あれは……」
喉が震え、頬が引きつる。
「あれは、私の心に刻まれた記憶だという事か……」
塩に覆われた終末の世界。人では抗えない圧倒的な力。
あまりの凄まじさに恍惚すら覚える。
それが彼の迷いの姿だった。
大聖堂に再びオルガンが響き渡る。
禍々しくそれでいてどこか愉悦を感じさせる旋律が。
一心不乱に鍵盤へと向かう青年に足音が近づく。
「私の心は決まりました」
振り向くことも、指を止める事もなく、青年は背後に
やってきた司教へと告げる。
「その曲は?」
紡がれ続ける音楽に司教は疑問を口にする。
「Etude of the Ruin……崩壊を表した習作です」
青年は淡々と答える。
「習作?」
「はい、私が体験した『災厄』は未だ表現し難い。全て
を識り、技巧を磨き、更なる高みへと登れた時こそ再現
できると思っています」
「それで、答えは?」
漸く青年の手が止まる。
「封聖省を希望します。塩の杭を研究する為に」
未だあの畏るべき災厄は彼の心に生々しく爪痕を残し
ていた。
だからこそ、彼はあえて己の人生を狂わせた塩の杭に
関わることを決意したのだ。
避ける事も可能だっただろう。だが彼の向上心はそれ
をよしとしなかった。
青年——ゲオルグ・ワイスマン。
彼の中で旋律は絶える事なく流れ続ける事となる。
まるで、心を冒す闇のように。 |