
クリックすると大きくご覧になれます
|
「和尚ー!」
あぜ道の方から、弾んだ声が聞こえた。
横の髪の毛をふたつの耳の上であげまきにした童子が、小さな包みを持って走ってくる。
和尚は担ぎかけた土嚢をふと下ろした。
両肌脱ぎのたくましい上半身に玉のような汗が光っている。
日に焼けた太い首の回りには、頭の後からつながっている長い三つ編みが一巡りしていた。
心の強さを物語る太い眉。優しく細めた目。
童子が跳ねながら近づいてくると、大きな手を広げて抱き上げた。
「あはははは…」
はじけたように童子が笑う。
水墨画のような空に、幼い笑顔が踊る。
豊かな実りもたらす大地のにおい。
雪解け水をごうごうとたたえる川。
切り立った山々。
たなびく雲。
なにもかもが、穏やかだ。
絵のような世界がここにはある。
遠くで、牛が鳴いていた。
和尚は肩に童子を乗せて、積み上げた土嚢に登った。
豊かな水をたたえて流れる川を見ながら、腰を下ろす。
童子は和尚の肩から飛び降り、いそいそと包みをほどいた。
竹の葉に包まれたチマキが三つ、転がり出た。
「おなかすいたろ、和尚」
「うん」
「母ちゃんが作ったんだ。うまいよ」
童子は、チマキをつかんで和尚の前に差し出した。
和尚も、チマキをつかんで童子の前に差し出した。
「いいよ、おいらは。
全部、和尚んだよ」
「一緒に食べよう」
「足りなくなっちゃうよ?」
和尚は、チマキの皮をむいて、童子の鼻先につけた。
ふんわりと香るクルミのにおい。
「ちぇっ、大喰らいのクセに、ムリしちゃってさ」
童子は手にしたチマキの皮をむいて、同じように和尚の鼻先に突き出した。
二人は一緒に笑って、互いの手からチマキを食べた。
「うまいね」
「うまい…」
和尚は、あっという間にひとつを平らげた。
童子は、自分がかじった分を和尚から受けとり、リスのように両手で持って食べた。
もぐもぐやりながら、上目使いに和尚を見る。
和尚は、残ったチマキに手を伸ばし、たった二口で飲み込んでしまった。
あまりにも豪快な食べっぷり。
童子はあきれた。
「もうちょっと味わって食べればいいのに」
「うまかった」
和尚は立ち上がり、また土嚢を担いだ。
「少しくらい、休みなよ…」
童子は、チマキを食べながらつぶやいた。
目の前の川は、かなりの水量だ。
今年は、雪解け水がだいぶん多い。
本格的な雨期が来る前に、すでに一度、土手が破れそうになった。
和尚は、黙々と土嚢を積み上げ、壊れかけた部分を修復している。
村の男たちは、どうして手伝わないのか?
いや、手伝わないのではなく、手伝えないのである。
今は田おこしのために手が離せない時期だ。
苗床を作り、田植えの準備を調えなければならない。
土手の修復のような予定に入っていない仕事は、どうしても後回しになっていた。
そこで和尚が、このやっかいな仕事を買って出たのだ。
童子は和尚を初めて見つけた時のことを思い出した。
去年、ふきのとうを取りに山へ入ったときのことだ。
まだ雪も残る寒々とした春の山に、それは落ちていた。
獣の骸のように、汚れて転がっている。
名残雪に半分埋もれ、縄をかけられ…
童子は最初、罠から逃がれたものの息絶えた猪だろうかと思った
しかし、縄と見えたのは長い長い髪の毛だった。
頭頂と側頭を剃り上げ、後頭の髪だけを残して三つ編みにする独特の髪型…弁髪である。
その生き物は、ぴくりとも動かない。
童子は、おそるおそる顔を近づけた。
ひゅうひゅうと、かすれるような息の音がする。
「大変だあ!」
童子は、この時点で初めて、人が倒れているのだと認識し、大声を上げた。
行き倒れの男は、村長の家に運ばれた。
貧しい村の中で、余分な布団がある家は、そこだけだったからだ。
男は、三日三晩というもの、目を覚まさなかった。
童子は自分が拾った手前、足繁く村長の家に通って、謎の大男を一生懸命介抱した。
泥にまみれた体を拭いてやり、手足のあちこちに出来たひっかき傷を手当してやり…。
その甲斐あって、四日目の朝、男はむっくりと起き上がった。
「わあ、気がついた!」
童子は大喜びで、みんなに伝えた。
女中が残り物の粥を温めて、運んできた。
男は瞬く間に粥を飲み込んだ。いや、吸い込んだ。
その後は、大変な騒ぎになった。
男が目覚めたことを聞きつけた村人たちが、わらわらと集まってくる。
変わった頭の男がどこからやって来たのか、なにをしゃべるのか、誰もが知りたがった。
村人たちは、ヤジ馬だと思われるのがイヤなので、芋だの豆だの団子だの、様々な見舞いの品を持って、村長の家に押しかけた。
弁髪の男は、次から次へと差し出される食べ物の全てを飲み込み、最後に、
「…うまい」
と、言った。
あまりにも率直で単純な第一声。
かたずをのんで男を見守っていた村人たちは、一斉にずっこけた。
ざわめきの中、村長が「おほん」と咳払いして、男の前に寄る。
「御坊(ごぼう)は、どちらからおいでになりましたかな?」
村人たちは、男の髪型から、きっと僧侶だと決めつけていた。
だから、村長も「御坊」と呼ばわったのだ。
果たしてそれは正しかったらしく、男は静かに合掌した。
しかし、村長の問いには答えなかった。
ただ
「この恩義、お返ししたく存じます」
と、短く言った。
それ以上は、なにも言わなかった。
「なんだよ、せっかく助けてやったのに」
「メシも食わせてやったのに」
「なんにも話してくれないのか?」
村人たちが、口々にぶつぶつ言い出す。
和尚は困惑したように、ちょっと首をかしげた。
ゆらり、と立ち上がって、家の中を歩く。
厨房に大きな青銅の水瓶があった。
高さは大人の胸程まで、胴は大人の一抱えと半分くらいか。
三本の脚がついており、土中に差し込んで固定する型のものだ。
和尚は水瓶の縁をつかむと、一気に引き抜いた。
中身はほとんど空っぽだったが、なにしろ青銅製である。
その重さは並大抵ではない。
和尚は軽々と水瓶を担ぎ、黙って外に出た。
村人たちは、わけがわからなかった。
あっけに取られたまま、思わず、異形の僧侶の後に続く。ぞろぞろと。
和尚を先頭にして、村人たちの列は村長の家を出た。

クリックすると大きくご覧になれます
|
やがて、和尚は川のほとりで立ち止まった。
青銅の水瓶を川に差し入れ、引き上げる。
満杯になったところを軽々と肩に担ぎ、また歩き始めた。
人々は、キツネにつままれたような面持ちで、その後に続く。
なんと、和尚は村中の家を回り、青銅の大瓶を傾けて、家々の水瓶を満たしていった。
水が足りなくなると川へ行き、またたっぷりと汲み上げる。
黙々と。
和尚は全ての家の水瓶を満たした。
最後に青銅の水瓶を一杯にして、村長の家の台所に戻す。
そして、合掌。
相変わらず無言だったが、村人たちには、和尚の望みがよくわかった。
ぱらぱらと拍手が起こり、みんなが笑い出した。
もはや誰も、和尚の過去について問おうとはしなかった。
誰かが、
「おまえさまのことは、青銅和尚と呼ぼう!」
と言った。
弁髪の和尚は合掌したまま頭を下げた。
それから、和尚は村外れの丘にある荒れ寺に移った。
寺といっても、本尊もない、庫裏もない、八角形に柱が建っているだけの小さな建物だ。
何故そこに建っているのかさえ、とっくに忘れ去られた古い亭である。
和尚は、すきま風も雨漏りも気にせず、八角亭で寝泊まりした。
日が昇る前に起き出して、村中の農作業を手伝い、地面が見えなくなるまで続ける。
毎日、毎日。
夏が過ぎ、秋が来て、やがて実りの時が来た。
和尚のたゆみない労働は、大豊作をもたらした。
この頃になると、村の誰もが和尚のことを好きになっていた。
村人たちは、大喰らいな和尚のために、入れ替わり立ち替わり、食べ物を運んだ。
貧しい村のこととて、せいぜい芋や豆の類ばかりなのだが、和尚はいちいちに合掌し、瞬く間に平らげた。
童子は、チマキを食べ終わるまでの間に、そんなことを思い出していた。
目の前では和尚が土嚢を運び続けている。
黙々と。
一言も発することなく、無愛想なようだが、まなざしは限りなく優しい。
村のために働くことを、心から喜びと感じている。
「おいら、和尚がいっとう好きだよ!」
童子は出し抜けに叫んだ。
「掟」・第一回終わり
|
|
©Nihon Falcom Corporation.
All rights reserved. |
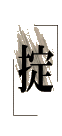

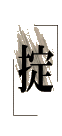

 クリックすると大きくご覧になれます
クリックすると大きくご覧になれます