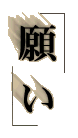

[
全一回 ]
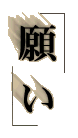 |
 [
全一回 ]
|
私はネイティアル。
まだ形を持たない。
私を呼び出し、望みを抱く者の心の力によって、初めて姿を与えられる。
私は力。
作用する力、それ自体。
人間から姿を与えられることによって、実世界に存在することができる。
私は、強大な無限のエネルギー…
「申しわけないけど。
わたくし、能書きには興味ないの」
人間の女は言った。
「要は、あなたが役に立つのか立たないのか。
わたくしの願いをかなえてもらえないのなら、無駄な時間を過ごす気はなくってよ」
こういう女を、人間の世界では気位が高いというのだ。
私はちゃんと知っている。
この女は、生まれてから二十年くらい経っているだろうか。
ちょうど思春期から青年期へ移ったところだ。
たっぷりとした亜麻色の髪、サファイアの青をたたえた瞳、バラ色の唇。
人間の男なら、確実に美人だと認識するだろう。
だが、細い眉をつり上げて、鞭を打つように鋭い言葉を放つこの様子では、あまり多くの個体が近づくことはないであろうと推測する。
気位の高いのは、幼年期からの成長過程によるものか。
女の住む環境は、経済的に恵まれている。
今こうして話しているのも、大多数の人間には手の届かない豪奢な屋敷の中だ。
女はフロイライン(お嬢様)と呼ばれて、屋敷中の人間たちからかしずかれる立場にある。
私は音声ではない声で語りかけた。
『それはこちらも同じこと。強い力を持たぬものに呼び出されたのでは困る』
フロイラインは唇の端を少しあげた。
「あなた、悪魔になれて?」
語調は鋭いが、まだあどけなさの残る声。
私は、おかしがるという感情を持たないが、フロイラインの言うことに興味を持った。
『悪魔…そう呼ばれることもある。また、神と呼ばれることも』
「悪魔でなければ、失せなさい」
フロイラインは手近にあるヌイグルミを引き寄せた。
ネズミを象ったつもりなのだろうか。
レモンのように不自然な黄色で、風船のように丸々としている。
できそこないのネズミはフロイラインに抱きしめられて、キューと小さな音を立てた。
『私はネイティアルだ。
ネイティアルは、呼び出す者の心に応じて、いかようにも形を変える。
すべては、マスターの心の向きと、力の強さ次第』
「では、悪魔になれるのね?」
『そう望むならば』
ネイティアルに善悪はない。
そもそも、善だの悪だの美だの醜だのといわれるものは、人間の価値基準にすぎない。
ネイティアルは力そのものだ。
ただ、そこにあって万象に作用するエネルギーだ。
どんな価値を求めるかは人間の勝手であり、私には興味のないことだ。
「安心したわ」
フロイラインはヌイグルミを抱きしめる腕をゆるめた。
「では、どんな悪魔になれて?」
幼い子供がおとぎ話の続きをせがむような調子で言う。
『なんでも、望み通りの姿になろう』
私は答えた。
『ネイティアルはマスターの望む姿に変化する。
できる限り、強い力を発揮できる姿を思い浮かべればよい』
フロイラインは、にっこり笑った。
私の姿が見えないので…何しろ、私にはまだ姿がないのだ…ヌイグルミに向かってうなずく。
黒いボタンで出来たつぶらな瞳と見つめ合っている様は、人間の子供によく見受けられる仕草だ。
高飛車な態度と比べて、違和感がある。
この人間は、一貫した悪への情念を持っているのだろうか?
価値観がなんであろうと構わないが、情念が弱いのは困る。
ネイティアルが強大になれるかなれないかは、呼び出す人間の情念の強さに依存するのだ。
そもそも、万能の力を持ちながら、何故マスターの手を借りなければならないのか。
それは、情念を持たないからだ。
私は力そのもの、エネルギーそのもので、方向性を持たない。
マスターが情念によって方向性をつけてくれなければ、自然の中に漂っているだけの存在だ。
だが、力である以上、力として最大に作用したい。
私の望みはただひとつ。
できる限り強い人間に呼び出されて、できる限り激しく世界に作用することだ。
『なぜ、悪魔を望む?』
私は尋ねた。
中途半端なマスターなら、関わり合いにはなりたくない。
弱いネイティアルとして召喚されたら最悪だ。
この人間がどのくらい強い情念を持っているのか、確かめる必要がある。
「ある男を…殺したいの」
フロイラインは瞼を半分だけ閉じた。
長いまつげの隙間から、青白い光が放たれる。
人間なら「ぞっとするほど冷たい」と表現するだろう。
幼い声も、言葉にそぐわない分、かえってすごみを帯びている。
「わたくしをふみにじった男…」
奥歯をかみしめる軋んだ音。
フロイラインはヌイグルミを睨みつける。
細い指が黄色い体に食い込み、ネズミの側面には十本の筋が浮かんだ。
なるほど。
私は少し安心した。
こういう話は、人間世界ではよくあることだ。
フロイラインの仕草があんまり幼げなので、二十歳の女であることを忘れていた。
そうそう。人間の持つ情念の中でもっとも強いのは愛憎だ。
愛するとか憎しむとかいうのがどんなものかは知らないが、人間たちがそのために様々な事件を起こすのは、よく見てきた。
特に、成体となった女のそれはすさまじい。
たとえば、私は、自らの喉を短刀で貫いた女を見たことがある。
その女は、自分の気に入った人間の男と連れ添うことができなかった。
それだけの理由で、生きることをやめてしまったのだ。
人間は、生き物なのに…
生き物とは、生きる意志を持ったもののことで、生きようとしないものは生き物の法則に反している。
その生き物・人間が、自ら命を維持することを拒否するとは?
生き物のクセに生き物の法則に合っていないこの行動は、不可解きわまりない。
だが、これは単に法則に合っていないというだけで、実際にあった出来事だ。
人間の愛憎は、自然の法則をねじ曲げてしまうほど、強い力を持っている。
「あの男を殺してやりたい!」
フロイラインは叫んだ。
私はうなずいた…もちろん、人間のような首があったらそうした、という意味だが。
『なんでも望むがいい。私はあらゆる武器となろう。
どのように殺す?』
「爪で引き裂く!」
フロイラインは右手の指を鉤型に曲げて空を切った。
…すばらしい。
人間の体を引き裂く爪か。
『どのような形の?』
なるべく詳しく想像してもらいたい。
それがそのまま、私の姿となる。
「大きな爪よ…砂漠の民の曲がった剣のような…月の光を映して、冷たく輝くの…」
『その爪で、なにができる?』
「あの男の皮を紙のように破って、肉を切り裂き、内蔵を引きずり出す。
手足は寸刻みに刻んで…銀の爪を赤く染める…」
おお。
たいていの人間なら、恐れおののくだろう。
なかなかよさそうな姿ではないか。
よし、もっと強く念じてくれ。
「いいえ…だめだわ」
フロイラインは急にため息をついた。
鼻より高くあがりかかっていたあごを下げ、額をヌイグルミに埋める。
『なぜだ? なかなか強そうな姿ではないか』
私は非をとなえた。
フロイラインはゆっくりと頭をあげる。
唇がゆがみ、あごに小さなシワが寄った。
「…生ぬるいの」
青い瞳が、さっきよりも一層鋭くなる。
復讐の炎が燃え立つ、といった表現をするべきだろうか。
「体を切り裂く程度で、あの男の犯した罪を許すわけにはいかない」
そうか。
確かに、爪程度では、まだまだ大したことはない。
大きな爪を持つネイティアルなら、ザラにいる。
私は最強のネイティアルになりたい。
では、どうする?
「炎…そう、炎で焼き尽くすのがいいわ…」
フロイラインはうつろに微笑みながら中空を見回した。
あたかも炎を眺めているようなまなざしだ。
「地獄の業火…全身の血が一瞬で沸騰してしまうほど熱い…ドラゴンのブレス…」
『ドラゴンか』
竜型のネイティアルは、見たことがある。
羽があったり、角があったり、姿は様々だが、たいていは激しい炎を吐き出す。
魔獣の中の魔獣。ドラゴンの一種になるのも悪くはないか?
「ううん、ドラゴンじゃ月並みね。もっと恐ろしいものがいい」
フロイラインは額に指を当てた。
「全身に炎をまとう魔人…もちろん、体の中にも炎が渦巻いている。
そうだわ、おなかの中に溶鉱炉を持っているの…それが砲弾となって…あの男の体を燃やし尽くすのよ。
あの男の肺には空気の代わりに炎が流れ込む…自分の肉が焦げるにおいをかぎらがら死ねばいいわ。
生きたまま、火葬にしてやる!」
感動的だ。
私は、熱く燃えたぎる何かを感じた。
…ああ、もしかすると、これが喜びという感情なのか?
人間の持つものがわかりかけた気がする。
フロイラインの情念が、私と融合しようとしているのか。
最強のネイティアルとして姿を与えられる時がきた。
紅蓮の炎をまとって、私は今、実体に…
「だめね、気に入らない」
フロイラインは、またヌイグルミに顔を埋めた。
私は実体をもらい損ねる。
相変わらず、漂うだけのエネルギーだ。
『なぜ? 炎の魔人のどこがいけないんだ』
「生ぬるいのよ…」
ヌイグルミに押し当てられたままの唇から、くぐもった声がもれる。
「炎の熱さがなんだと言うの?
わたくしが受けた痛みは、火傷なんかじゃ贖えない。
この重苦しく、つぶされそうな…」
フロイラインは、機械仕掛けの人形のように頭をもたげた。
あどけないえくぼと共に、残酷な微笑みが広がる。
「…つぶす…あの男を踏みつぶす…くくく…」
いいぞ、頼もしくなってきた。
その冷酷な笑みがいい。
「重たい岩…いいえ、鋼鉄のハンマー…手足を叩きつぶし、頭蓋骨を砕いて、脳髄を地面にブチまける…」
幼さの残る声が、地獄の場面を描写する。
私は、うっとりした。
『それで、鋼鉄のハンマーは、どんな形なのだ?』
「両手についているの」
『手があるのか。人に近い形か?』
「そうね。だけど、とんでもなく大きいわ」
『どれくらい?』
「あの男を、ゴキブリみたいに踏みつぶせるくらい!」
フロイラインは立ち上がって、足を踏み鳴らした。
そして、床にぺったり座り込んだ。
おいおい…
私はあきれた。
『いったい何が気に入らないのか』
フロイラインは、ヌイグルミをなで回した。
「だってェ…」
『まだ生ぬるいか?』
「うん」
私は、ため息をついた…いや、肺と鼻か、もしくはそれらに近い器官があるならそうしたかった。
フロイラインが作り出しかけた姿は、いずれも申し分ない。
巨大な爪を持つ魔獣も、炎の魔人も、両腕にハンマーをつけた巨人も、私にとっては魅力的に思えた。
『だったら、全部採用すればいいのではないか?』
私は急かした。
『大きな爪も、大砲も、ハンマーのついた腕も、全部つけてはどうだろうか』
そう提案してやると、フロイラインは、やっと顔を上げた。
青い瞳に再び情念が燃えさかっている。
亜麻色の髪が風もないのになびいた。
肩先から青白い靄が立ち上っている。
「そうね…」
フロイラインはうっとりと微笑んだ。
「あの男を切り裂く…焼き尽くす…叩きつぶす…」
フロイラインはつま先立ちになって、ゆっくりとステップした。
ワルツでも踊るように。
「全部、やってやればいいんだわ」
まんまるなヌイグルミを相方に見立てて、優雅に回る。
青い靄が、かげろうとなってフロイラインの体中からたなびいた。
「あなた、あの男を引き裂いてくれて?」
『もちろんだ。爪をくれるなら』
「焼き尽くしてくれて?」
『大砲の最初の餌食はそいつにしてやる』
「そして、踏みつぶすのよ!」
『ああ、踏みつぶす!』
私は背中にぞくぞくする快感を覚えた。
…背中?
「あはははは…」
フロイラインは声を立てて笑った。
亜麻色の髪の毛がみんな逆立っている。
全身を包む青白いほむらが、太い柱となって立ち上った。
「さあ、思い浮かべてくれ、最強の姿を!
私を呼びだしてくれ!」
私は叫んだ。
声が出た!
フロイラインの声に似た、高い音だ。
彼女の情念に導かれて、私は実体を持とうとしている。
今や、私たちは共通の意志を持ち、最強の力をもってこの世界に作用しようとしているのだ。
ああ、フロイラインの心が流れ込んでくる。
マスターとネイティアルはひとつの心を共有するのだ。
私は、自分が青白い光に包まれているのを見た。
まぶしい…
私に目が出来始めているからだ。
かん高い笑い声を鼓膜に感じる。
耳も出来ているのだな。
この音と光を胎盤として、私は生まれるのだ。
もう漂うだけの存在ではない。
マスターによって実体を与えられたネイティアルだ。
そう…最強のネイティアルなのだ…!

予想していた状況とは全く不釣り合いな音がした。
「なぜ…?」
フロイラインの大きな目が近くに見える。
金色のまつげがぱちぱちとせわしなく合わさっては離れた。
私は、フロイラインに抱かれている。
「うそつき。どうして悪魔にならないの…?」
フロイラインはゆっくり膝をつき、そのまま座り込んだ。
私はフロイラインを突き放そうとしたが、手が短すぎてできなかった。
「ちち、ち、ちゅー…!」
言葉の代わりに間抜けな鳴き声が出る。
爪も、大砲も、ハンマーの腕もない。
あるのは風船のように膨らんだ黄色い体と、バナナのように曲がった尻尾だけ。
私は、出来損ないのネズミのヌイグルミだ!
「なぜなの?」
フロイラインはうつろにつぶやいた。
ゆっくりと、私を抱きしめる。
そのとたんに、すべての理由がわかった。
フロイラインの腕から、情念のうねりが波となって流れ込んでくる。
ああ…胸が締めつけられる…この想いは、なんなのだ?
「…わたくしは、あの人を傷つけることなどできない…」
頭の上に、ぽたぽたとあたたかいものが降ってきた。
なんてことだ。
それなら、なぜ、爪や大砲やハンマーを望んだのだ?
人間の考えることはわからない…
ボクは疑問に思ったけど、だんだん不思議だとは感じなくなってきた。
きっと、ボクの心とフロイラインの心が、おんなじになったからだね。
ねえ、ますたぁ。
ボクは、ますたぁが大ちゅきだよ。
だから、ボク、世界で一番かわいい「ねーてぃある」になるよ……
願い・終わり
©Nihon Falcom Corporation.
All rights reserved.