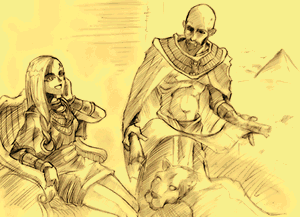「…やれやれ、まいったね」
叔父は小さくため息をついた。
「もう出てきてもいいよ」
王女はセクメトと一緒にベンチの陰から這い出した。
「あの女史の相手をするのは大変だ…同情するよ」
「でしょう?」
王女は腕を組んだ。
「叔父上が逃がしてくれなかったら、私は日が沈むまでアレを聞き続けるの」
「苦労するなあ」
「苦労するんです」
王女と叔父は、顔を見合わせて笑った。
叔父は細い指で、ちょっと王女の肩を押した。
促されて、王女は叔父と並んで図書館へ向かった。
そこは、唯一の逃げ場なのだった。
優しい叔父上…王弟デペイは、変わり者で通っている。
国王ヘセティ四世のたったひとりの兄弟でありながら、政治などには一切かかわらない。
ひとつの王家にふたりの男児が生まれたならば、権勢を争って深刻な事態へと発展することも珍しいことではないだろう。
しかし、叔父は権力に全く興味を示さなかった。
ただ、書物に埋もれ、学問の世界で遊ぶことを愛していた。
派手な王宮の人間関係とも没交渉で、あまり外に出ることもない。
祭りや宴に出なければならないときにも、病と称して欠席する場合が多かった。
デペイ…ワニという意味の猛々しい名前を持ちながら、もの静かな学究の徒なのである。
王女は、そんな叔父に尊敬の念を抱いていた。
派手好きでお世辞ばかりの貴族たちや、口うるさい家庭教師たちとは違う。
そして、公務にばかり一生懸命な父王、ヘセティ四世とも違っている。
叔父は知的で、なにより王女をかわいがってくれるのだ。
王女と叔父は、図書館の中に入った。
ここは、叔父の城。
王宮の中心部からはずいぶん離れた、小さな蓮池の隣に建っている。
日干しレンガを積み重ね、白い漆喰で塗り固めた四角い空間。
四方の壁は、小さな窓が開いているところ以外、みんな書棚だ。
パピルスの巻き物と外国から届いた粘土板が、ぎっしりと詰まっている。
これを全部読んだのかと思うと、それだけでも叔父を尊敬したくなる。
「何のお話がいい?」
叔父はパピルスを編んだ椅子を勧めながら言った。
王女は書棚を見回し、少し考えてから、
「ハモン王の話がいい」
「またかい?」
「いいの。何度でも聞きたい」
王女は書棚の前に行き、パピルスの巻き物を一本、引き出した。
叔父はそれを受けとり、役者のように恭しく広げて、おじぎをした。
「では、メル建国の父・ハモン王の物語…」
王女はパピルスの椅子に腰かけて、拍手した。
セクメトが椅子の脚に体をこすりつけながら、ごろんと横に伸びた。
叔父は、普段のもの静かな態度からは想像もつかないほどの明るさで、英雄の冒険を面白おかしく語り始めた。
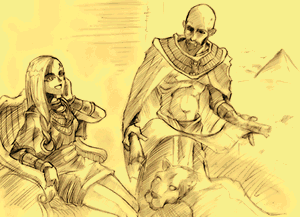
英雄ハモンは、ハピの河に咲く蓮の花から生まれた。
知恵と力と勇気を持った立派な若者だった。
しかし、いつもその力をもてあましていた。
ある時、ハモンの前に一羽の黒朱鷺が現れた。
朱鷺は英雄の行くべき道を示し、冒険の旅へといざなった。
怪物退治、美女の救出、世界の果てでの宝探し。
ハモンは、どんな困難にも勇敢に立ち向かい、鮮やかに乗り越えて行くのだった。
王女は身を乗り出し、目を輝かせて物語に聞き入った。
楽しい時間が、矢のように過ぎさって行く。
「…最後に、ハモンはこの地に戻って、王となった。
長い間、平和に国を治めた後、冥界へと旅立っていった。
人々は亡骸をミイラにして、メルの塔に安置した。
副葬品として、たくさんの財宝も一緒に納められた。
それは、人々がハモン王をとても愛していたことの証だった」
デペイ叔父は、そこまで語ると、パピルスから顔を上げた。
西の窓から、オレンジ色の光が斜めにさし込んでいる。
いつの間にか、夕方なのだ。
メル・レー・トゥが拍手すると、叔父はパピルス紙を丸めて、もとの通りにとじた。
長々と伸びきって、いびきまでかいていたセクメトが、大あくびとともに目を覚ます。
王女と叔父は図書館の四角い空間から外に出た。
西の空が赤い。
都を取り巻く城壁の向こうに、メルの塔が浮かんでいた。
ハモン王が眠っているとされる墓所だ。
それは、砂漠の丘にそびえる巨大な三角形。
塔と言いながら、細長いものではない。
底面が正方形で、それを囲む四面の壁が正三角形、神秘の角度に囲まれた、いにしえの建造物。 そもそも、この塔があるから、この国はメルの国というのだ。
王女は叔父と並んで、赤く燃えるメルの塔を眺めた。
太陽が、ハピの河を進む船のようにゆっくりと、メルの後ろに隠れて行く。
涼やかな夕風が舞い、王女の伸ばした黒髪がオレンジ色の波となってきらめいた。
ふと、気付くと、叔父のまなざしが王女の方に向けられていた。
思い詰めたような、今にも、涙をこぼしそうな。
王女は戸惑って、一歩あとずさった。
叔父は、いつにも増して聞き取りにくい低い声でつぶやいた。
「かわいそうに」
かわいそう?
王女は暴れる髪をおさえながら、首をかしげた。
「君は、シェメウに行かねばならない。
そうして髪を伸ばし、シェメウの習慣を教え込まれ…」
叔父はメルの方を向いた。
「人質になりに行くのだ」
「叔父上」
王女は、じゃれて頭をこすり付けてくるセクメトの首を抱いた。
頬をくすぐる短いたてがみが、柔らかくて心地よい。
メル・レー・トゥは、自分の逃れられぬ宿命のことを思った。
生まれる前から決められていること。
それは、祖国を守るために。
メルの国は、クムトと呼ばれる広大な土地の上にあった。
クムトには、南から北へとハピの河が横たわり、網の目のように支流を広げている。
ハピは、その源流を見た者がないくらい、長い長い河だ。
ただ大地を横切って流れるだけで、魚を育て、肥沃な土を運び、大地を潤す。
有史以来、人々はハピに寄り添い、ハピの恩恵を受けて暮らしている。
メルもそうやって出来た国の一つだ。
クムトには、ハピの河に沿って無数の国が連なっている。
そして、無数の国があるならば無数の力関係が存在する。
四代前の王の時代の話だ。
メルは豊かで、芸術と学問の花が咲き乱れていた。
だが、いくら文化が発達していても、軍事力に劣れば、たちまち他国の侵略を受ける。
ハピの中流域にあって、黙っていても作物が実る豊かな国土は、あらゆる国から狙われた。
そこで、最も強い国、シェメウに保護を求めたのだ。
その条件が『王権をシェメウに預けること』であった。
メルの国の王位継承制度は、複雑な仕組みになっている。
神事に基づいた独特のもので、この世界を作った夫婦神の結婚に由来している。
通常、王になるのは王家の長男だが、王権は男児のものではない。
王家に生まれた長女…第一王女のものだ。
この王女と結婚することによって、はじめて、メルの王となる。
王家は神の一族とされていたから、人間の血を混ぜず、神同士で結婚するのだ。
ヘセティ一世は、王権の象徴である第一王女をシェメウの王に嫁がせることによって、同盟を結んだ。
宗教的な意味では言語道断の、とんでもない奇策である。
しかし、実質的な執政者である王家の長男は、メルの国に残すことが出来る。
こうして、形式的な王権だけをシェメウに預け、実の部分は従来と変わらぬまま、国内に残したのだ。
以来、王家に生まれた最初の姫は、シェメウへ嫁ぐことに決まっている。
国内に残った王家の長男は、姉妹のためにシェメウへ貢ぎ物を続けていた。
だから、人質なのだ。
いつか…いや、近い将来、シェメウからの求めが来る。
その時は、メル・レー・トゥ自身の意志がどうであれ、嫁かなければならない。
叔父は姪の頭をなで、再び、
「かわいそうに…」
とつぶやいた。
燃え立つ太陽がメルの塔の向こう側に、完全に没した。
赤い空が、夜の刷毛になぞられて紫に染まり、やがて墨色に沈んだ。
第四回・終わり
|
|
©Nihon
Falcom Corporation.
All rights reserved. |