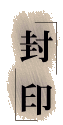

[
第二回 ]
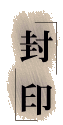 |
 [
第二回 ]
|
少女はヒースの野を越え、町までやってきた。
尼僧院を出てきたはいいが、どこへ行けば四本腕の巨人に会えるのか。
前からやってくる百姓風の男を捕まえて、尋ねてみた。
「四本腕の巨人を知りませんか? 逆立った髪の毛が、炎のように燃えているんです」
百姓風の男は首をかしげ、目を丸くした。
そして、少女をまじまじとみつめると、肩をすくめて立ち去っていった。
少女は、他の人に聞いてみることにした。
「四本腕の巨人を知りませんか?」
当然のことだが、こんなことを質問されて答えることができる者などありはしない。
誰もがあきれ、面食らい、果ては頭がおかしいのだと勘違いして、気の毒そうな目をしながら去っていった。
少女は雑踏の中に取り残された。
尼僧院しか知らない彼女に、町はあまりにも冷たかった。
「お嬢ちゃん、誰を探してるんだい?」
若い男が声をかけてきた。
革のベルトに手を引っかけ、少し猫背気味に背を丸めている。
「あの…実は…」
初めて話し掛けてくれた人物に対し、少女は質問するのをためらった。
さすがの世間知らずも、質問の内容がおかしいのかもしれないと思い始めたのだ。
猫背の男は親切そうに笑って、
「俺はここらじゃ、ちょっとしたカオなんだ。きっと力になれるよ」
と、優しく言った。
親切な言葉に勇気が出て、巨人の話をしてみることにする。
もちろん、ネイティアル・マスターのことや、母のこと、闇の者のことは語らず、ただ夢の巨人を探して尼僧院を出てきたのだと言った。
男はちょっとあきれたような顔をしたが、すぐ笑顔に戻って「大変だねえ」と同情してくれた。
「どうやって探すつもりなの?」
「それが、全然あてがないんです」
「探してる間、宿はどうするの?」
「尼僧院に泊めてもらいます」
「この町には、尼寺はないよ。一番近いのが、多分あんたが出てきたとこだね」
「そんな…」
男は今度こそ本当にあきれて肩をすくめた。
「とにかく、か弱い女の子をほっぽっておくわけにはいかないな。
俺の知り合いの家に頼んであげるよ。
少しの間、そこで厄介になりながら、探してみたらどうだい?」
少女は迷ったが、結局、男の世話になることにした。
断るのも失礼だし、今夜の宿に困っているのも事実だから、渡りに船と好意に甘えることにしたのだった。
男はみすぼらしい下宿屋の二階の部屋に少女を案内した。
小さな窓からは酒場ばかりが見え、お世辞にも上品な界隈であるとはいえない。
しかし、贅沢の言える立場でもなし、少女は丁寧にお礼を言って、男に頭を下げた。
男は照れたのか、そそくさと部屋から出ていった。
少女は藁を盛り上げただけの寝台に座り、小さくため息をついた。
あたしって、なんておバカさんだったんだろう。
お母さんのことを聞いて、何も考えずに尼僧院を飛び出してしまった。
四本腕の巨人を探しているなんて、普通の人が聞いたら、頭がおかしいと思うに決まってる。
それでも今日は親切な人に会えて、こうして安全な寝床まで与えてもらうことができた。
神様に感謝しなくちゃ…
少女は母の形見のペンダントを握りしめ、寝台に向かって膝をついた。
どうか、あの親切な人に、幸せが訪れますように。
……コツコツ。
祈っていると、扉を叩く音がした。
「はい」
少女は立ち上がり、扉を開けた。
「!」
突然、少女の両腕に痛みが走った。
二人の見知らぬ男に、両脇を押さえつけられる。
「なにをするんですか!」
少女は叫んだ。
「なるほど、上品だな」
太った髭面の男が廊下のほうから現れた。
「へへ、だから言ったでしょ。尼寺から飛び出してきたばっかりなんでさ」
髭面の男の後ろから、さっきの親切な男がやってくる。
「助けて下さい!」
少女は助けを求めたが、親切なはずの男は両手を揉みしだきながら髭面の男にへつらっていた。
「ちょっとばかり、おかしなことを口走りますが、これだけの上玉ですからね。
高く買い取ってくだせぇよ」
初めから、こうするつもりだったのか。
少女が悟った時には遅かった。
髭の男は人買いであり、少女は売り飛ばされようとしているのだ。
抵抗しようとしたが、無駄だった。
いくら足をばたつかせても、両腕を大の男に押さえつけられている。
…助けて!
少女は誰を呼ぶでもなく、頭を天に向けた。

「オオーッ!」
突然、胸元に下げたペンダントが光り、野太い雄叫びが響いた。
悪党どもは眩しさに目がくらみ、一瞬まぶたを閉じる。
次に目を開けた時、少女の右腕を押さえていた男が昏倒した。
「ほっほっほっ!」
満足そうな笑い声。
角のついた兜をかぶった白髭の老人が、ハンマーを振りかざしている。
老人は勢いが余っているのか、踊るようにステップを踏んでいる。
「じじい、どこから現れた!」
少女の左腕を押さえていた男が、老人に立ち向かう。
「オオーッ!」
老人は身ごなしも鮮やかに飛び上がると、ハンマーを一振りした。
ハンマーが火を噴き、男の頭を横ざまに殴り付けた。
フッ飛ぶ男。
「見たか! わしゃあ、まだまだ現役じゃ!」
驚いた人買いと猫背の男は、壁のほうへと後ずさる。
「オオーッ!」
老人は三たびの雄叫びをあげると、瞬く間に二人の男をなぎ倒した。
それから。
少女は謎の老人に守られて、怪しい界隈を抜け出し、町の外に出た。
誰も追ってこないことを確認すると、少女はへなへなと座り込んだ。
「ありがとう、おじいさん」
お礼を言うと、なんだか涙が出てきた。
…怖かった。
少女が泣き出すと、老人はオロオロして周りを歩きまわった。
「困った。困ったのう。あんさまが泣くと。泣くと…わしも…」
老人はくるくる歩きながら「わしも泣けてくるんじゃ。うおーい、おい…」
と、子供のように泣き出してしまった。
あまりのことに少女は泣くのをやめて目をぱちくりした。
老人は両足を投げ出して座り込み、おいおいやっていたが、少女が泣き止んだのに気が付くと、同じように目をぱちくりした。
少女が思わず吹き出すと、老人もまた嬉しそうに笑った。
「面白いおじいさんね」
「面白いか。あんさまが面白いなら、わしも面白い」
二人は顔を見合わせて笑った。
「おじいさんが来てくれなかったら、あたし、今頃どうなっていたことか。
でも、どうして助けてくれたの?」
「そりゃあ、あんさまがお呼びなすったからじゃ。
あんさまをお守りするがこのヘピタスの務め」
老人はどんと胸を叩いた。
「ヘピタス…ヘピタスさんていうのね、おじいさん」
「おや、わしをご存知ないのか?」
ヘピタス老人は、信じられない、というふうに大きなまなこをしばたたいた。
「そのハンマーを持っとらっしゃるに」
少女の胸のペンダントを指す。
「これ?」
少女はペンダントに手を当てた。
「これは、お母さんの形見なの。ネイティアルを呼び出すために…あ!」
今頃気づく。そうだ。この老人は、ペンダントが光った時に現れたのだった。
「あなたはネイティアル?」
「そうじゃ。わしこそ火のネイティアル・ヘピタスさまじゃ」
そう言えば、ヘピタスの持っているハンマーはペンダントとそっくりだ。
少女はまじまじと老人を見つめた。
小柄な少女よりもまだ背が低く、ずんぐりとした体つき。
ごわごわに突っ張った白い髭。うれしそうに笑った口の前歯が一本欠けている。
ネイティアルというからには精霊なのだろうが、想像していたようなフワフワしたものではない。ずっしりとした実在感にあふれている。
本当に、この老人がネイティアルなら…。
あたしは、院長先生の言う通り、ネイティアルを呼び出したことになるんだわ。
「ねえ、ヘピタスさん。四本腕の巨人を知っていて?」
同じネイティアルなら、夢の巨人のことを知っているかもしれない。
「四本腕の巨人? おお、ダルンダラじゃな」
ヘピタスは、あっさりと名前まで出した。
「まさか、あんさまは、あのダルンダラを呼び出せるんか?」
「いいえ」
少女は夢の話をした。
「なるほどのう」
と、ヘピタスはうなずいた。
「ダルンダラは幻のネイティアルじゃ。
炎の神殿で、封印を解かれるのを待っていると言われておる」
「封印?」
そう言えば、夢の中で巨人は「われを解放せよ」と繰り返し言っていた。
「もしかすると、あんさまこそ、ヤツの封印を解く者なのかもしれんのう」
ヘピタスはぼそりとつぶやいた。
「どうしたら、会うことが出来るかしら」
「さてのう。ヤツはもともと古い時代の炎の神での。
炎の神殿に行けば、手がかりがあるかもしれん」
「それはどこに?」
「わからん」
ヘピタスは無邪気に首を振った。
どうやらここで話は行き詰まったようだ。
しかし、ダルンダラが古い時代の神だというなら、その神殿も遺跡として、どこかに残っているかもしれない。遺跡を探すのなら、なんとか手がかりがあるだろう。
少なくとも「四本腕の巨人を知りませんか?」と尋ねまわるよりは現実的な質問である。
「わかったわ。炎の神殿を探しましょう。ヘピタスさんも手伝ってくれる?」
「わしゃあ、あんさまの行かっしゃるところなら、たとえ地獄の果てまでもじゃ。
ずっとお守りしますわい」
第二回・終わり
|
©Nihon
Falcom Corporation. All rights reserved. |