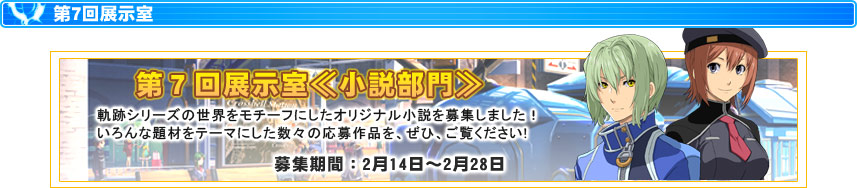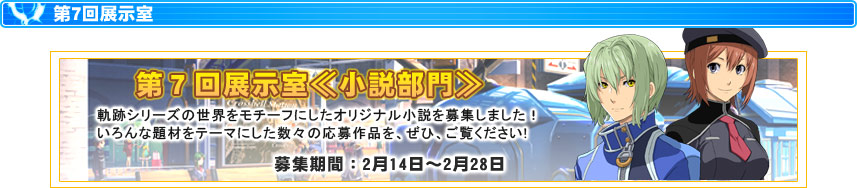■Sillia
| 【タイトル】 |
帝国内乱秘譚 |
| 【作者】 |
Sillia |
だから ね
からかう様に声はそこかしこから。
あたし ほしいの
そこで誰かが止めればよかったのだ。けれど宮城の最奥、皇帝の寝所には、皇帝に意見できるものなどそんざいしない。普段なら傍仕えの小姓もいたが今は誰も隣の部屋にはいなかった。
薄暗い寝所にいるのは、後に傾国王または狂情王と揶揄され個人名を忘れ去られた皇帝。
そして皇帝の寵愛を一身に受け宮城内を好き放題に闊歩する女。元は踊り子だか占い師だかの身分だが街に出た皇帝に見出されただけのはずの。
あのへやいっぱいに きらきらした ほうせき
その声は蔓のように皇帝を絡めとり。
その瞳は赤く輝いては皇帝を狂気の底に堕とす。
だから とってきて
もはやその皇帝の周囲には女しかいなかった。反発するものは処刑され、それを恐れたものは皇帝から離れていく。
皇帝はただ一人残った女の愛を失うことを恐れた。暴れ馬と化した黄金の軍馬の手綱を取れるものはおらず、次の日皇帝が部下や臣民に、一切合財の財産を献上するように命令することを止められなかった。
さすがにこの命令に従うものはおらず、完全に女に狂わされた皇帝を相手に兵や貴族を含む帝都の民は蜂起した。長夜時代といわれる内乱の始まりである。
後にも先にも一般臣民まで巻き込んで混乱したのは、長いエレボニアの歴史においてこの一度きり。
皇帝の名を記すことも忌避された当時の書物はすべて名を黒く塗りつぶされ、今ではその下の真名を探り当てることは出来ない。
己の血で濡れる玉座にて彼が残した言葉は、
「尾を喰らい身を喰らい国を喰らう竜となった」
である。現在でもこの言葉の意味は解明されていない。完全に狂っていた、死の間際に精神が癒えた、諸説あるが今だ真相は闇の中である。
そして、皇帝を狂わせ、宮城を狂わせ、帝都を狂わせ、一つ間違えば帝国全土にまで騒乱を広げかねなかった原因である、赤い目をした女は。
すべて終わったときにはどこにも存在しなかったという。
自害したのか、隠れて逃げたのか。
これもまた、歴史の襞の奥に埋没したままである。 |