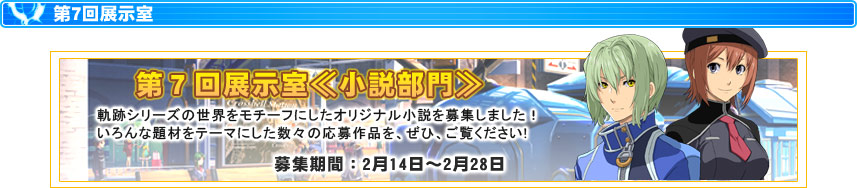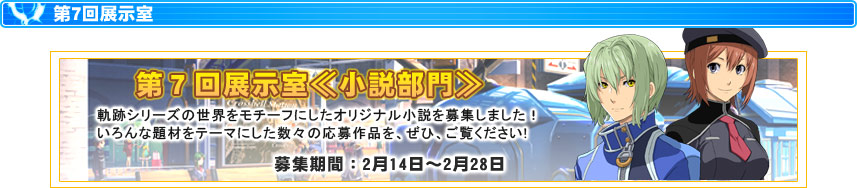■親父フェニックス
リベール南部にある工業都市ツァイス、その南端部に
あるのがエルモ村である。
東洋の様式を多く取り入れたそこは、
その独特な雰囲気と、名物になっている温泉が
旅行者の疲れを癒す観光名所である。
そしてその名物を一手に引き受けているのが紅葉亭。
エルモ村の裏山には源泉がありそこから温泉を引いてい
るが、村の広場にある公共のものを除けば紅葉亭にしか
引かれていない。
それはポンプ室の大きさ故のことかもしれない。
その女将をしているのが通称マオ婆さんである。
正確な齢はわからないが、中央工房のラッセル博士と旧
知であることを踏まえれば
それぐらいの年齢なのだろう。
紅葉亭は厨房のエド、販売のアディ、清掃他手伝いの
リーシア、そして彼女で切り盛りしている。
露天風呂というものはリベール人には馴染みが浅いの
で敬遠するものもいたが概ね好評で、本日も上々の客入
りだった。
突飛なものもいない。かつては風呂場でリュートを弾
くという剛の者もいたが、それもない。
マオは勘定台で頬杖をついた。
「はぁ……」
ため息が零れる。別に悩み事があるわけではない。
不意に空いた時間によって空気が吐き出されただけだ。
しかし他者にはそう見えなかった。
「マオ婆さん、何かあったの?」
そう言って顔を覗き込むのはリーシアである。
その顔を見てマオが思ったのは、
この子はオリビエさんに夢中だったね、
という感想だった。
「なんでもないよ」
「ならいいけど……」
少々不満そうに消えていくリーシア。
その後姿を見てまたため息を一つ。
なんてことはない、最近のマオの関心は半年前ほどに
お手伝いとして雇ったリーシアなのである。
今までは村にいる子どもの中では年齢が高いことも
あってかお目付け役といった立場にいたが、
それでも現状に不安を覚えていたのだろう、
掃除の手伝いを申し出てきた。
マオとしてもそれに文句はない。
仕事ぶりにも文句はない。
しかし、ちょっとした感情を揺さぶられた。
成人というには若いが年頃の少女。
その長い青みがかった髪。
「あの子ももう十七か……」
脳裏に過ぎるのは故郷の風景。その中で楽しげに走る
一人の少女。小柄で、そして笑う少女は次第に身体を大
きくしていく。
しかし顔は見えなかった。当然である。
もう何年も会っていないのだ。
成長した顔はわからないが、しかし美人であることだろ
う。身体も均整は取れているはずだ。
「はぁ……今頃何してるかねぇ……」
マオはリベールを故郷と思っている。
しかし久しく見ていない家族に似た姿に懐古の念を
覚えるのは仕方のないことだった。
どこかにいるだろう孫を想ってマオは空を見上げた。
温かな木の天井が見えた。
「くしゅ」
「あらリーシャ、風邪?」
「そんなはずないですけど……
(内気功でひきませんし)」 |