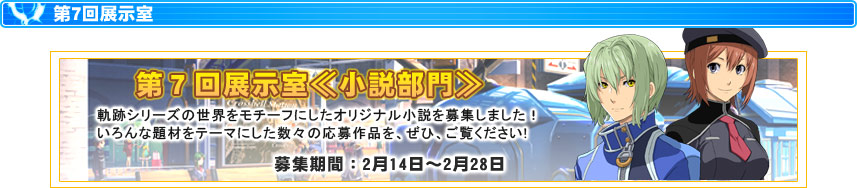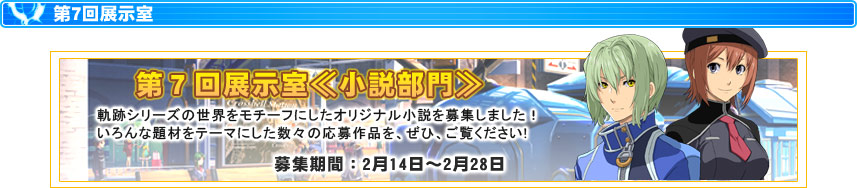■ユウ
私はいつもの様にリベールの澄んだ大空を仰いだ。
穏やかに流れる雲の傍で、飛行船が規則的な機械音を奏
でている。
その船の甲板に目をやると、そこに一人の男がいた。
ブラウンの髪、歳は二十歳前後だろうか、甲板の柵に手
を掛け項垂れている。
周りの乗客が嬉々として空からの風景を楽しむ中、男だ
けが異次元にいるかのような重々しい雰囲気だ。
私は何故か興味を引かれ、目を凝らした。
男は…泣いていた。
ただ静かに泣いていた。
男の瞳からは、涙が次から次へと溢れていた。
それが私と男の出会いだった。
数日後、私はグランセル城下にある広場の木陰から、街
路を行き交う人々を眺めていた。
私の仕える主人は、街の様子を知る必要があるのだが、
理由あって外を出歩けない。
代わりに自由な私が主人の瞳の代わりをしている。
小一時間居座ってみたが、特に変わった様子はない。
主人への報告を頭の中で整理していると、ベンチに一人
の男が座った。
忘れもしない、あの男だ。
まだ彼の傷は癒えていないのだろうか。
丸まった背中に、以前と同じ暗い影を落としている。
ただ、今日の男は泣いてはいない。
膝の上にノートを広げ、右手に握られた羽ペンを動かし
ている。
何を書いているのだろう、私は小首を傾げた。
「ここは…もっと綺麗な言葉が良いな」
男は書いた文字を塗り潰し、また書き、そして塗り潰す。
単語一つ一つに情熱的という程の拘りを持っているよう
だ。
おそらく、この男は小説書きなのだろう。
「………駄目だ。気分が乗らない」
男はノートを閉じると、フラフラと立ち上がり、そのま
ま私の前から去った。
ベンチにはペンが残されていた。
羽は黒く汚れ、毛先がバサバサになっていた。
この羽では、どんな鳥でも空へ舞い上がる事は不可能だ
ろう。
私は無意識にそのペンを拾い上げていた。
「あら?それはどうしたの?」
主の元に帰った私に、主が不思議そうに問いかけてくる。
私は出会った男の事を伝えた。
「そう…良い小説家になって欲しいですね…」
主は優しく微笑むと、ひとつの提案したい、と言った。
「その方に少しでも元気になってもらえるように、協力
してくれない?」
大切な主の為に、私は二つ返事で頷く。
「ありがとう、ジーク」
翌日、男は自分が置き忘れたペンを探す為、例のベンチ
に来た。
もう一人、友人らしき男も一緒だ。
「あったか?」
「うん。けど…この羽は…」
男がペンを友人に見せると、友人は感嘆の声を上げた。
「立派な羽だな…!お前こんな上等な羽ペン使ってたの
か?アントン」
アントンと呼ばれた男はしばらく目を白黒させていたが、
意を決したように瞳を見開き空を見上げた。
「絶対に世の中に認められる詩を書いてやる…!」
男の背筋は真っ直ぐに伸びていた。
その背中に羽根が生えたように、私には見えた。
この先、男はどの様な軌跡の物語を描いていくのだろう
か。
私は男の成功を祈りながら、果てしなく続くリベールの
澄んだ大空へと舞い上がった。 |