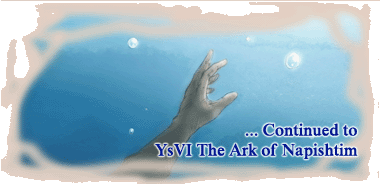船縁に駆け寄ると、私は海に視線を走らせた。
東の海上に、波を分けて迫ってくる艦列が見えた。見守るうちにそれは舵を切り、砲列の並ぶ船腹をずらりとこちらに向けて揃えた。
「な、なんでこんなトコに
ロムンの艦隊がいるんだよっ!」
テラにはまだこの光景が信じられないようだった。この危険な海域にあれほどの大船団が現れたのだから無理もない。
と、そのとき、艦列の中を閃光が跳ね回った。
「そら、初弾が来るぞ! 抜錨(ばつびょう)いそげ!」
艦橋からラドックの怒号が届いた。私たちは巻き揚げ機に群がり、必死にそれを回した。やがて背筋の寒くなるような唸りが響いたかと思うと、目の前の海にまとめて砲弾が降り注ぎ、《トレス=マリス》号全体を滝のような海水が襲った。

「大丈夫だぞ、必ず逃げ切れる」
水煙が晴れると、ラドックは船員たちを励ましながら、矢継ぎ早に指示を出した。ラドックの命令は単純明快だった。とにかく錨(いかり)が抜けたらその瞬間に帆を張って逃げる。それだけだ。
また、遠方の艦影から光が走った。と、同時に、急に巻き揚げ機が軽くなった。錨が海底から離れたようだ。
艦橋から号令が響き渡り、帆は目一杯広げられた。錨鎖を波間に引きずって《トレス=マリス》号はじりじりと前進し、やがて水柱の間を割るように力強く波を切り始めた。
ラドックはすぐに針路を北西に定めた。それは《大渦》の外周に沿って進むことを意味した。渦の流れに乗り、その勢いを利用して敵を引き離そうというのがラドックの狙いだった。確かに"禁忌"の海域に近づけば、ロムン艦も追っては来ないだろう。だが、もし舵を取られ、深みにはまってしまえば、今度は自分たちが《大渦》に呑み込まれてしまう。危険な賭けだと思ったが、ラドックの表情に迷いは見られなかった。信じられない話だが、笑みすら浮かべていた。
 ラドックは操舵手のジェドと2人掛かりで舵輪にしがみつき、この神業に挑んだ。一体どれだけの力が掛かっているのか、彼らがわずかに舵を切り直すたび、船尾全体がびりびりと痺れるように震えた。だがラドックたちは見事な均衡をもって船を操り続けた。《トレス=マリス》号は一気に船脚を速めたが、決して渦に近づくことはなく、舵を切ればいつでも外周へと脱出できる絶妙な位置を滑るように走り続けた。砲撃を続けるロムン艦隊は見る見る離れていき、私たちは賭けに勝ったかに思えた。
ラドックは操舵手のジェドと2人掛かりで舵輪にしがみつき、この神業に挑んだ。一体どれだけの力が掛かっているのか、彼らがわずかに舵を切り直すたび、船尾全体がびりびりと痺れるように震えた。だがラドックたちは見事な均衡をもって船を操り続けた。《トレス=マリス》号は一気に船脚を速めたが、決して渦に近づくことはなく、舵を切ればいつでも外周へと脱出できる絶妙な位置を滑るように走り続けた。砲撃を続けるロムン艦隊は見る見る離れていき、私たちは賭けに勝ったかに思えた。だが、前方に現れた黒い船影が、わずかに芽生えた希望を粉々に打ち砕いた。艦首に燦然と星光を輝かせるそのロムン艦は、渦のやや外側を私たちと並ぶように疾走していた。
待ち伏せされたのだと、私は直感した。初めから艦隊は二手に分かれ、私たちが一方との駆け引きに夢中になっている間に、行動を読んで先回りしていたに違いない。ロムンにもラドックの操船を完璧に読み切るほどの人物がいたのかと、私は妙な気持ちになった。
整然と並ぶロムン艦の砲列が、手の届きそうほど近くに見えた。真っ白な光が、その上を音もなく走った。
「転舵するぞ! 掴まれ!」
砲声の代わりに、ラドックの声が轟いた。船首が急激に西へ向かって滑り、船体は一気に渦へと向かい転回を始めた。ラドックは《大渦》に突入することを選んだ。なす術もなく砲撃にやられるくらいなら、最期まで足掻いてみようというわけだ。船尾から響く舵のきしみが、まるで《トレス=マリス》号の悲鳴のように聞こえた。だが努力も空しく、一発の砲弾が後部甲板を吹き飛ばした。

短い悲鳴が走った。それと同時に、見えない空気の波が船尾から押し寄せてきた。背後を見ると、飛沫となって吹き上がる木片の向こう、宙を舞う誰かの姿があった。叩き付けられ、甲板に投げ出されたのはテラだった。彼女の体は、引きちぎられた舷側へから海へと、目の前を滑り落ちていった。私は咄嗟に手を伸ばした。
テラの青い瞳が私を見上げていた。その奥に、逆巻く潮の流れが見えた。

「バ、バカ!
余計なことすんなよっ!」
テラは何か喚いていたが、自分の鼓動の音ばかりがうるさくて、私には殆ど何も聞こえなかった。一息ごとに、彼女を支える右腕から感覚が消えていった。私は反動をつけ、渾身の力を込めてテラを甲板へと引き上げた。体勢を戻そうとしたとき、わずかに船が傾いだ。 そして、私は碧い波の合間へと吸い込まれていった。
<<Back