綿を裂いたような薄雲が、海の果てに向かって流れていた。西を目指し、船はアトラス洋をひた走っていた。
エディスを出港してから丸1日。釈然としないまま船倉の一角で夜を明かした私たちは、丸窓から差す陽の光で目を覚ました。テラが船倉にやってきたのは、その昼下がりのことだった。
船縁に腰掛けた彼女は、まず無理やり船に乗せたことを詫びた。どさくさ紛れに相手を船に乗せてしまうという手は、彼女の父親の十八番だそうだ。
その父親とは他でもない、あの眼帯男のことだった。名はラドック、通称《隻眼のラドック》。エウロペを旅する間に、私も一度ならずその名を耳にしていた。ロムン帝国の船舶ばかりを付け狙い、3つの大洋に渡って手配を受けている反骨の大海賊だ。彼の首には莫大な懸賞金が懸けられているというから、酒場に突っ込んできた帝国兵たちの勢いも、なるほど道理で凄まじかったわけだ。

《イブール一家》として母親アルガや兄弟たちと盗賊稼業に手を染めていたテラが、父親ラドックの率いるこの《トレス=マリス》号に乗り込んだのは、今から2年前のことだったそうだ。
「もっと広い世界を見たくなったんだ」
丸い空を行く雲を目で追ったまま、テラはサンドリアを離れた理由をそう言い表すと、にっこり私に微笑みかけた。両親の職業どちらにも『賊』とつくことを考えれば、彼女はまっすぐ育っていると言えた。まだあどけないその笑顔には、3年前と変わらぬ光が満ちていた。
船長室の戸を引くと、ドギの大声が響いた。
「《カナンの大渦》だとぉ?」
私の姿に気づくと、ラドックはわずかに顎を動かし、こちらの視線に応えた。だがドギにはそんな素振りも目に入らないらしく、海図に手の平を叩き付けると彼は吐き捨てるように言った。
 「とにかく無理だ。
「とにかく無理だ。あんたら、正気とは思えねえぜ」
一瞬の静寂のあと、「ふむ」とラドックは一声うなり、おどけたように片方の眉を持ち上げた。
「……相棒さんはこう言っているが」
彼は眼帯に隠された右目で私を見つめ、
「アドル=クリスティン。
お前はこの話、どう思う?」
と、海図の一点に太い指を下ろす。そこには巨大な渦が描かれていた。《カナンの大渦》という波型の飾り文字が、その脇に添えられていた。
これが"世界の果て"だとラドックは言った。
アトラス洋の遥か西に"禁忌"とされる海域があるという話は、私も各地の船乗りたちから聞いていた。"世界の果て"、"魔の海域" ——呼び名こそ様々だったが中身はどれも同じで、そこに差し掛かった船は1隻残らず海の藻屑と化してしまうという類の話だった。
正直なところ、私はその手の噂をあまり信じてはいなかった。そうした話の多くは、聞く人によってころころと内容が変わり、到底事実に基づくものとは思えなかった。そもそも遠洋への航海は危険極まりない難事業だ。世界の端から落っこちなくとも、遭難する理由は他に山ほどある。
だが、この《大渦》の話は、そういう世間の噂話とは次元が違うものだった。
ラドックはもう一枚、新たな海図を卓上に広げた。たちまち私の両目はその図上に釘付けとなった。それは詳細な《カナンの大渦》の記録だった。蜘蛛の巣のように走る無数の方位線、その根元に列をなす日付、船の沈没位置を示す×印から漂流物の流れを意味する矢印まで、私は息を詰めて見つめた。記述はあまりに精密で、とても絵空事とは思えなかった。近づくものすべてを呑み込む《大渦》——それは確かに存在するようだ。
やがて私は、海図の中央部に広がる空白に気づいた。渦の内部と思われるそこには、ただ白い紙が続くばかりだった。
ラドックの指が、ちょうどその中心で止まった。「アドルよ」と彼は私に呼びかけ、そして微笑みながら言った。
「ここが渦の中心——
そして今、俺たちが目指している場所だ」
胸の奥に力強い鼓動を感じ、私は改めて眼下の渦を眺めた。
《カナンの大渦》、その先に広がるまだ誰も見たことのない天地……。ラドックの語る世界には、私の求めるものすべてがあった。
「どうやら答えは出たようだな」
眼帯男はあの満足気な笑みを浮かべ、ドギの方を向いた。私の相棒は、もうとっくにこちらの気持ちをお見通しだったようだ。彼は諦めたようにうなずくと、肩を落とし、そして深々と溜息を吐くのだった。
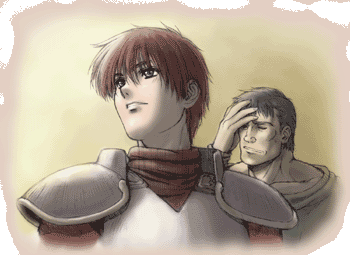
| 舳先の切る波の先から、飛魚たちが矢のような速さで飛び出していく。薄い膜のような羽を広げて、彼らはゆうに50メライ以上も飛行することができるようだった。 その後の一週間に及ぶ航海は、私にとって心躍るものとなった。 《トレス=マリス》号は、軽快な船脚でアトラス洋を西へと突き進んでいた。 |
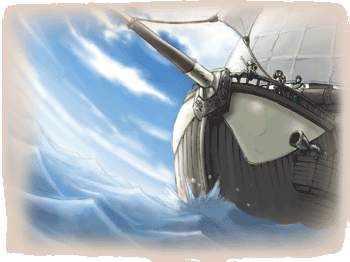 |
波と戯れるイルカたちの仕種や、滴るように沈む偉大な夕陽の姿に、私は目を奪われた。限りなく変化を続ける大洋の光は、世界に備わる無限の可能性を見る者に教えるようだった。
だが、ただ楽しんでいるわけにもいかなかった。船の中は一つの小さな社会のようなもので、乗り込んだ者は必ず何かの役割を担わなければならない。働かざるもの食うべからずというわけだ。その掟通り、私たちは甲板の清掃や洗濯といった雑役を手伝うことになった。船乗りの仕事について多少の経験があった私は、すぐ帆の巻き上げなどの操船作業にも参加させられるようになった。一方のドギも、船員でもないのにと始めは手伝いを渋っていたが、気づいたときには力仕事全般で頼りにされるようになり、お陰で2人とも数日後にはすっかり船員が板につき、他の乗組員たちからも仲間として受け入れられるようになっていた。
《トレス=マリス》号には、実に様々な地方の人間が乗り込んでいた。
船の中は一つの社会だと言ったが、私の体験したこの航海に限っては、『社会』というより『世界』の方が適当だったかも知れない。
サンドリア出身のテラ、褐色の肌を持つカマラはアフロカの生まれ、操舵手のジェドや航海士のグエンに至っては、オリエッタの更に東方からやって来たという具合だった。これまで訪れた各地でも、多地域の人々が共存する姿を見てはいた。だがやはり人々は互いの違いを意識していたし、どこかで異邦人であることを弁えているようにも見えた。しかし、この船はそうではなかった。
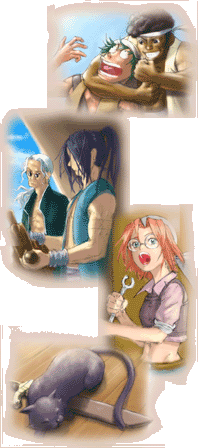
見ず知らずと言っていい私たちにも、彼らは親切だった。船長のラドックを除けば、子供の頃に読んだ『海賊の物語』に出てくるような荒くれ者はこの船にはいなかった。変な言い方だが、これで立派な海賊行為を働けるのだろうかと心配になるほどだった。うっかり私がその感想を口にすると、老航海士のグエンは、それは斬り込みをしていたような古い時代の話だと鼻で笑い、今の海賊はココだよと白髪頭を拳骨で小突いた。
普段、船の運行を司っているのは、このグエンと、もう一人の東洋人、ジェドの2人だった。グエンが進路を定め、ジェドが舵を切る。伸ばし放題の長髪を適当に束ねたジェドは、その風貌と寡黙な性格からは想像できないが、何かと面倒見の良い人物で、この船の副長的な役割を果たしていた。どちらかというと我の強い乗組員が多い中、口数が少ないからこそ、彼は皆に信用されているようだった。あのラドックも、ジェドたちの決定には口出しすることがなかった。
遥か東方から来た彼らの指示に従い、エウロペ、アフロカ、オリエッタから寄り集まった船員たちが手足となって働くことで、この《トレス=マリス》号は動いていた。彼ら乗組員たちの間には何の壁もなく、そこには一人一人の人間がいるだけだった。
飛魚の群れは姿を消していた。
錨鎖の滑り落ちる重い響きが、甲板を伝って足元を震わせていた。
きっと嵐が来るのだろう。
帆桁の上から、私は西の空に渦巻く鉛色の雲を見た。
大洋の只中に錨を下ろし、《トレス=マリス》号は停泊の準備を進めていた。
西の方角がにわかに曇り出したのは、ちょうど陽の下り始めた頃だった。進むにつれ空は暗さを増し、すぐに頭上は一面の煤色で埋め尽くされた。
水平線には、低く乳色の霞が立ち込めていた。嵐に見舞われている海域は、遠くからは白く煙って見える。あの辺りも豪雨に襲われているのだろうと私は思った。だが、それにしてもはっきりと見え過ぎた。まるで遠くに巨大な白波でも立っているようだった。
それが《大渦》の外周だと知ったのは、停船してからしばらく後のことだった。
薄暗い船室の中央に陣取ったラドックは、両の手を広々と海図についたまま、私たちがもう《大渦》の間近まで来ていることを告げた。そして、これからしばらくこの海域に錨泊し、《大渦》に入るための『きっかけ』を探すことになると彼は説明を続けた。
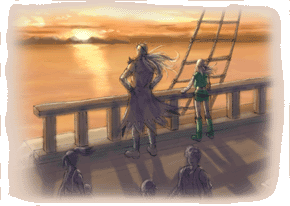
"綻び"と、ラドックはそれを表現した。
「渦の中にある安定した流れ──
それが"綻び"だ。
その流れに乗っていけば
中心までたどり着けるはずだ」
ラドックの言葉を口の中で繰り返しながら、私は西の彼方を眺め続けた。渦の外周では、波が泡となって沸き立っている。"綻び"が現れると、それは黒い滲みのように見えるという。
目を皿にして私は水平線を見つめた。どこかに"綻び"があるかも知れない。そう思うと、海に目をやらずにはいられなかった。だが、空と海の継ぎ目には白い波が続くばかりだった。
どれほどそうしていたことだろう。ふと、頭上から甲高い声が聞こえた。見上げると、檣楼(しょうろう)に立つテラが何かを指差していた。
もしや"綻び"を見つけたのかと、私は振り向いた。だがすぐにそうではないことに気づいた。テラの腕は、渦とは反対の方に向かって伸びていた。
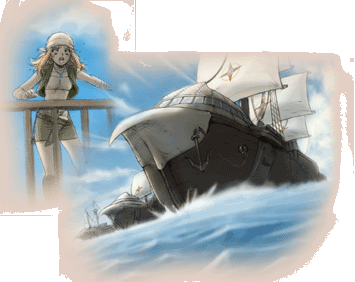
艦橋のラドックに向かい、彼女はありったけの声で叫んだ。
「親父! ロムンの艦隊が来た!」