私たちの前に現れたのは、体格のいい中年の男と、ショールで顔を隠した若い娘だった。男の右目は眼帯で塞がれていて、彼が大人しく町で暮らしているような人間でないことを教えてくれた。
娘の方はただじっと、男の背後に隠れるように控えていた。ちらりと私の方を見たような気もしたが、視線は綾織のショールの奥に隠され、窺い知ることはできなかった。
「赤毛のアドルだな?」
男はそう言い、油断なく光る片目で私を見下ろした。私の返答を待つこともなく、彼は続けた。
「どうだ、俺たちと一緒に
"世界の果て"を見に行かないか?」
世界の果て?
私は自分でも気づかぬうちに、男の顔を見つめ返していた。
そんな私の瞳を捉えると、男は満足げに唇の端を持ち上げた。まるで猟師が罠に掛かった獲物を確かめるような顔だった。
まさにそのとき——
何の前触れもなく、いきなり入り口の板戸が弾け飛んだ。
男の肩越しに、ふわりと宙に舞い上がる扉が見えた。右手の指先でフォークを支えたまま、私は回転しながら上昇していく木の板を見つめていた。世界のすべてが、蜜に浸かったようにゆっくり動いていた。指先からこぼれ落ちるカード、空中に螺旋を描く貝殻、椅子ごと床板に倒れ込む船員の肩……。その一瞬は今も凍りついたように鮮明で、克明に思い起こすことができる。
扉は天井近くまで吹き飛んでいった。それを追いかけるように、闇色の戸口から走りこんでくる影があった。椅子を蹴散らして近づいてくるそれは、鉛色の甲冑に身を包んだロムン兵だった。
と、誰かに強く腕を引かれ、私は我に返った。ショールの娘だった。
「来なよ!」
そう告げるより早く、彼女は私を引っ張って走り出していた。転げ落ちるようにして椅子から抜け出すと、床に手をつきながら私は必死で彼女の後を追った。すぐ背後で眼帯男がドギを叱咤する声が聞こえた。娘は風のように階段を駆け上がり、私をバルコニーへと連れ出した。ちょっと後ろを振り返り、またすぐ私の腕を掴むと、ショールを翻して隣家の屋根へと飛び移る。兵士たちの罵声に追いたてられるまま、私もその後に続いた。

| すでに辺りはとっぷりと暮れていた。私たちは蒼い闇の中を潮風に向かって走り続けた。民家の中庭に飛び降り、肩幅ほどもない路地を潜り抜けると、突然目の前が開け、一隻の船が現れた。知らぬ間に、私たちは港へと来ていた。 娘は手早く舫(もや)い綱を外すと、一気に梯子を駆け上って船に乗り込んだ。船縁(ふなべり)から手招きする彼女に促されて、まず私、続いてドギが四つんばいになりながら、そして最後に眼帯男が、続けさまに甲板へと転がり込んだ。その途端、待ち構えていたように三角帆が風を受け、船体はきしみをあげて動きだした。 |
「主帆(しゅはん)降ろせ! 行くぞ!」
眼帯男の叫びに、帆桁から一斉に声が応えた。岸壁にロムンの兵士たちが集まり始めた頃には、船はすでに岸を離れ、真っ白な2つの月の浮かぶ沖へと船首を向けていた。見る間に兵士の掲げる松明は遠くなり、気づいたときにはもうエディスの灯もなく、船が大洋へと乗り出したことを、私たちは知るのだった。
何もかもがあまりに唐突だった。
私は呆然と、エディスのあった方角を見つめていた。あの酒場での語らいが、はるか昔のことのように思えた。隣ではドギが、やはり呆気に取られたような顔をして座り込んでいた。
「何て顔してんのさ。
まったくだらしないんだから」
赤々と燃える舷灯のそばに、いつの間にかあの娘が立っていた。
彼女は身をひねると、無造作にショールを解き放った。灯火を透かして蜜色に揺れる前髪の奥から、荒野の空のように青い瞳が現れた。私のことを覗き込むその視線には、どこか見覚えがあった。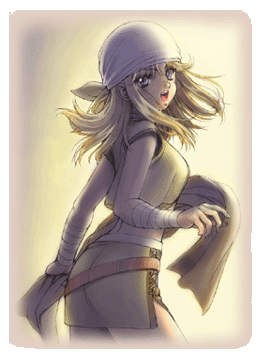
「アドル、久しぶりだね!」
私はまだ混乱していたが、記憶は次第に形を取り戻し、やがて鮮やかに蘇ってきた。
——彼女の名前はテラ。
3年前、私がサンドリアで知り合った盗賊の少女だった。